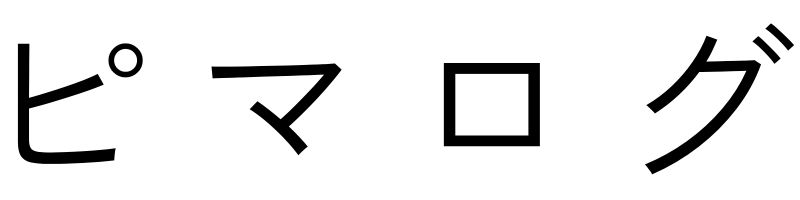洋書を読みながら、ノートに書き写す。面倒なのはたしかですが、読書効果や学習効果は大きいです。
今回は実際に僕がやっている洋書の書き写しについて、やり方と注意点を解説したいと思います。
洋書の書き写しはシンプルに

まず最初に、僕がやっている洋書の書き写し方法について説明します。やり方はいたってシンプルです。
- 洋書の書き写し方
- ① 印象に残ったところや疑問に感じた文を抜き書き
- ② そのあとに自分の感想や意見を書き込む
こんな感じでむずかしいことは何もしません。【抜き書き→感想を書く】という流れだけです。
僕もかつては色ペンを使ったり、ノートにレイアウトに凝ってみたりしましたが、長続きしませんでした。
ノートの書き写しに時間をかけすぎると、洋書を読む時間が減ってしまいます。これでは本末転倒なので、ノートの書き写しは最低限でOKとし、読む時間を最優先で増やすのがベストです。
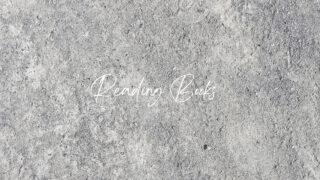
書き写すと洋書の読み方が変わる
- 洋書を書き写すメリット
- ■ 洋書を能動的に読むことができる
- ■ 復習がしやすく、記憶に残りやすい
- ■ 文の構造や単語のスペルにまで意識が向く
- ■ 読み終えたあとの満足感
洋書を能動的に読むことができる
書き写すことなく、ただ単純に読むのは趣味や娯楽としては十分です。しかし、本を読んで仕事に活かしたり知見を得たいのであれば、ただ読み進めるだけでは不十分です。
書き写すことを前提に読書をすると「どこを書き写すか?」というところに意識が向くので、結果的に「自分にとって重要なところはどこか?」という目的意識を持って本を読むことができます。
意識して読むことで、記憶への残り方も段違いですから、読書の効果は大きくUPします。

復習がしやすく、記憶に残りやすい
本を読んでもスグに忘れてしまう、という人は多いと思います。せっかく読書をするなら、自分の知識として定着させたいですよね。
そのためにも、洋書の書き写しが役に立ちます。
印象に残ったところや疑問に思ったところをノートに書いておけば、あとで振り返ったときに要点だけをチェックすることができます。
本を読んで線を引いておくのもたしかに有用ですが、ムダな文章も一緒に目に入ってくるので、ノイズも混じってしまいます。
純粋に重要な箇所だけを振り返ることができれば、時間や集中力の節約にもなるので良いことづくめですよね。
また、いつも使っているノートであれば日常的に何度も読み返せると思います。そうすることで反復による刷り込み効果がはたらいて記憶の定着にもつながります。
僕はスケジュールも読書記録も1冊のノートにまとめているので、書き写した箇所も自然と読み返すように習慣づけられています。
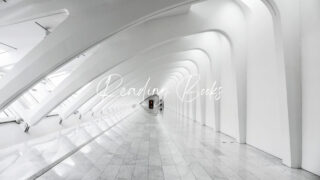
文の構造や単語のスペルにまで意識が向く
洋書を書き写すということは、文章を最低でも2回は読むことになります。さらに、書く過程で文の構造や単語のスペルにまで意識が向くので、理解力がUPします。
ただ読んでいるだけだと気づけないポイントに気づくことができるのも、書き写しのメリットです。
たとえば僕の場合、書き写すことで「これって、倒置が起きてるのか」とか「この単語のスペル、間違って覚えてた…」というポイントに気づくことが多々あります。
こういうのに気づけると、洋書を書き写しって効果的だなと実感します。
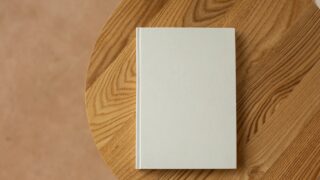
読み終えたあとの満足感
趣味でも仕事でも、なにかを終えたあとは達成感や満足感を得たいですよね。それがあるのとないのとでは、モチベーションに大きく差が生まれます。
洋書を書き写したあと、英文がびっしりと書き込まれたノートを眺めるのは何ともいえない充足感があります。
こういったメンタルの部分も僕は大事にしていて、小さくてもいいので日常的に達成感を得られるようにするのは大切だと思います。

洋書を書き写すときに意識してやるべきこと

人それぞれ、やり方はあると思います。今回は僕が洋書の書き写しをするときに意識していることをピックアップして紹介します。
- ■ 抜き書きだけで満足しない(感想&意見も添える)
- ■ 凝ろうとしない(色ペンは3色まで)
- ■ 単語や文法を意識しながら書き写す
- ■ ブツブツと音読しながら書き写す
抜き書きだけで満足しない
洋書を読んで、印象に残ったことや疑問に思ったことはどんどん抜き書きしましょう。ただし、文章を丸写ししてそれでおしまい、というのはおすすめしません。
というのも、抜き書きだけするのであれば、本に線を引いてあとで参照すればいいだけの話だからです。ノートにわざわざ書き写すメリットは小さいと思います。
そうではなく、【抜き書きをする→それに対する自分の感想・意見を書く】というところまでやりましょう。
そうすることで、あとで振り返ったときに「読み返す価値のあるノート」になります。

凝ろうとしない(色ペンは3色まで)
最初にもお伝えしたとおり、僕の洋書の書き写しはいたってシンプルです。使うのは3色ボールペン1本と1冊のノートのみ。
色ペンの数が増えると、そのぶん凝りたくなるし、ペンを持ち替える回数が増えるので時間と手間がかかります。
洋書ノートはとにかくシンプルに。レイアウトも色も深く考えなくてOKです。
ちなみに、使うペンとノートは愛着が持てるものを用意するのがおすすめ。ちょっとでも気分が上がるアイテムを使ったほうが、洋書の書き写しが楽しくなります。
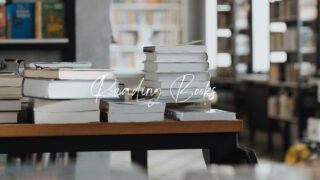
単語や文法を意識しながら書き写す
せっかく洋書を書き写すのであれば、何も考えずにやるのではなく、単語や文法を意識しながら書き写しましょう。
主語と動詞はどれか?副詞はどの位置におかれているか?関係代名詞はどう使われているか?
こういったポイントを意識しながら書き写すと、文法力UPを図ることができます。
また、単語を書くときもスペルミスなどをしないよう、正確に書くようにしましょう。

ブツブツと音読しながら書き写す
洋書を書き写す目的は人それぞれだと思いますが、僕は発音やスピーキングにも役立つように読んでいます。
そのためには、黙って書き写すのではなく、文をブツブツと発音しながら書き写すのがおすすめ。
発音してもしなくても書き写すスピードに差は生まれないので、せっかくなら手だけでなく口も動かしましょう。同じ時間を過ごすのであれば、最大限の効果が得られるほうがいいですからね。

時間と手間がかかるので、万人向けではない

洋書の書き写しは効果があると思いますが、当然ながら無理にやる必要はありません。
人それぞれ好みがあって、ノートに書き写すのが苦痛という人もいると思います。
そういう人は書き写しはやめて「黙読する」と割り切るか、音読するのがおすすめです。
文字を書いたり、ノートを作るのがそこまで苦痛ではないという人がトライしてみるのが良いと思います。
iPadなどのノートアプリを活用する方法も
iPadなどでノートアプリを使えば、違う気分でノートが書けるのでおすすめです。
ノートに書く=勉強感が強いから苦手、という人も多いと思いますが、iPad などのタブレットでノートアプリを使えば、紙のノートとは違う感覚で書き写しができます。
実際、僕はiPad のノートアプリとApple Pencilでノートを書くことがありますが、いつもとは違う気分で書けるので楽しいです。なんというか、遊んでる感覚に近いのかもしれません。
また、iPad にはスプリットビューという2画面機能があるので、Kindleとノートを1つの画面で開くことができます。洋書を読みつつ、すぐにノートを書くというのが1画面で完結するので非常にシームレスで使いやすいです。

洋書を書き写すときのコツ【まとめ】
- ■【書き抜く→感想や意見を書く】だけ。シンプルに徹する
- ■ 書き写すと記憶や知識に定着しやすい
- ■ 読むだけではわからない文の構造や単語に気づける
- ■ 発音したり音読しながら書き写すと効果倍増
- ■ ノートアプリを使うと、楽しく書き写しができる